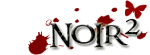 ― ノワール・2 ― 刻印(4) |
仄かに鼻腔を擽る甘い香りが焚き込められていく。 閉め切られた室内でくゆる煙に、くらりと軽い眩暈を覚えた。 毛足の長い絨毯。据えられたベッドは三、四人が乗っても余裕がありそうにみえる。 深い紅色のベッドカバーの上に下ろされ、琴音は戸惑いながらあたりを見回した。 乙夜の部屋に行くものだとばかり思っていたのだが、ここは高層マンションの一室だ。 生活に必要なものは何一つないようにみえる。誰かが暮らしている場とは到底思えない。 「ここ……どこ?」 「僕名義の部屋」 立ったままの乙夜がスーツの上着を脱ぎ、ネクタイを寛げる。 はずされた腕時計がコトンと音をさせ、サイドテーブルの上に置かれる。 動作のひとつひとつは流れるように行われた。 足音をたてない乙夜がベッドに片膝をつき、軋む音がわずかにする。 「琴音」 身を乗り出した乙夜が、琴音の耳元で囁く。近い筈のその声が、何故か遠く聞こえた。 思考が蕩けたように曖昧になる。なのに体の芯は相変わらず疼く。火照る。 ふるりと頭を振っても変わらず、香を吸い込むだけそれがひどくなっていくことに琴音は気付いた。 「乙夜くん……この香り、な、に?」 「――直に気持ちよくなるよ」 乙夜の声にあわせるようにゆらと身体が揺れる、座っていることも覚束無い。 琴音の体がぐらりと横に傾いだ。 ああ倒れる、と霞む意識の中に浮かんだがもう自由に手足を動かすことすらままならなかった。 ベッドに沈む前に乙夜の腕に受け止められ、くたりと力が抜ける。認識できる世界が曖昧になっていく。 首筋に顔を埋めるた乙夜から小さく舌打ちを聞いた気がした。 もう痕跡はないはずのそこにきつく口付けられる。痛みよりも焼け付くような熱さを感じた。 「僕の忠告をきかなかったね。……いけない子だ」 「ごめん、な……さ、い」 責められるまま、琴音は乙夜に許しを請うていた。 目の端からぱたぱたと涙が零れる。頭の片隅で、なにかおかしいと思う。 感情の抑制が効かない。押し寄せる波に包まれるように理性が希薄なものになって行く。 「――怖かった?」 ぽつりと尋ねられ、琴音はひっとしゃくりあげた。 力の入らない腕を精一杯伸ばして、乙夜にしがみ付く。 「こわかっ……た……っ」 「もう彼に手出しさせない」 あやすように背をさすられ、琴音の胸に、ここ数日の不安が一気に甦る。 「……違う……辰巳さんも怖かった、けど。乙夜くんが、いなくなちゃったことが、怖かった……っ」 もう帰ってこないのだと思ったことも、会えないのだと思ったことも、簡単に捨てられる存在なのだと思い知らされたことも。 全てを吐露し、興奮に荒く息を繰り返す琴音を、乙夜は細めた目でじっと見ていた。 「――何故君は、僕から逃げないんだろう」 自嘲するように乙夜が言う。 どうして逃げる必要があるのだろう、と琴音は不思議な思いで乙夜を見つめた。 乙夜が離れていってしまうことをこそ琴音は恐れている。 なぜ逃げないのかと問われれば好きだから、としか答えようがないが、それは言ってはいけない気がした。 「――乙夜くん、わたしね、成績あがったの」 なんと答えればよいかわからくて、脈絡のないことを口走った。 乙夜が驚いたように瞬いて、ぷっと吹き出す。 「そう、おめでとう。教えた甲斐があってうれしいよ……何かご褒美をあげようか」 「なんでも……いい?」 「いいよ、何がほしい」 秘密を聞き出すように、乙夜が琴音の間近で囁く。 琴音は、燻っていた灰が再び燃え立つように、抑えようのない欲が染み出してくるのを感じた。 「――乙夜くん、が、ほしい」 一度だけ躊躇った後、琴音は乙夜と唇をあわせた。 自分の涙の味がするキス。 瞬間、乙夜の唇が僅かに震えたような気がしたが、両手で頬を包まれ滑らかな舌を差し入れられ、理性は消えた。 親指の腹で耳の後ろをなぞられ、ぞくりと深いところが疼く。 目を閉じた琴音に、乙夜は何度も唇を重ねる。 口腔内を探られ、歯列をなぞられ、否応なく誘い出された舌が絡まりあう。 衣擦れの音が遠くに聞こえる。自分の纏っている服が脱がされているのだと琴音が気付いたのは、胸の赤く色づく先端を乙夜に食まれた時だった。 「……あ……っ」 胸元をくすぐる乙夜の髪が見下ろした視線の先にある。 ゆっくりと乙夜の重みをかけられ、紅色の中に琴音の背は沈んだ。 腕に引っかかったままのブラウスが中途半端に琴音の動きを制限する。 胸を覆っていた白い下着は上へずらされ、白い乳房が乙夜の前に晒されている。 ふくらみにそって撫でていた手が薄紅色の頂を軽く引っかき、舌先で悪戯に弄ばれている乳房とは違う、むずがゆいような感覚に琴音は切ない息を漏らした。 「……ん、や……っ」 硬くなった果実を、かりっと音をさせるように食まれる。 繊細ではあっても男性のものであると一目でわかる手の中で、琴音の乳房がゆるゆると形を変えていく。 乙夜のやわらかな髪が肌をくすぐる感触すら、いまの琴音にはたまらない刺激となった。 「あ……あ……ん」 押さえようとしていた声が、我慢できずに喉から漏れ出る。 脇腹の薄い皮膚に舌を這わされ、肌がぞくりと粟立つ。 乙夜が琴音の膝を割り、足の間に滑り込む。 膝裏に手を差し入れられ、片足を持ち上げられた。 指先で花弁を押し開かれる。蜜はとろりと満ちている。 執拗な愛撫で敏感になっていた剥き出しの芽を、じゅっと音をたてて吸われ、艶やかな悲鳴と共に琴音の背中が反った。 確かめるまでも無く、さらに蜜が溢れ、零れたことがわかった。 「ん……、あ、や、乙夜くん、それはやだ……っ」 琴音の懇願は乙夜への抑止力とはならない。 ぐちゅっと淫靡な響きで、琴音の中に乙夜の舌が忍び込む。 「……ぅ、いつ……乙夜く、ん……も、いやぁ」 直接的な刺激を与えてくれる指とは違う。 けれど丹念に花弁の中をなぞられ、ざらりとした感触に琴音の腰が浮いた。 「欲しい?」 主語のない言葉は、けれど何をさしているか明白だった。 理性の消えかけた琴音が、濡れた瞳でこくりと頷くと、眼を細めた乙夜が、琴音の腿に両手をかけた。 「乙、夜……」 「少しだけ我慢して」 柔らかく肌を撫でられ、力を抜く。 びくっと琴音の全身が痙攣した。 「い……っ! や、いた……乙夜く……あっ!」 一体何が起きたのかわからず、琴音は肘を支えにやや上体を起こした。 足の内側、付け根付近に乙夜が牙を突き立てている。 ずくずくと熱をもつ。何かを無理やり注ぎ込まれているような酷い痛み。 涙で視界が琴音の霞む。きりきりと痛む頭、体が強張る。 焦らされたり拘束されたことはあっても、乙夜が琴音に酷い痛みを伴う行為を強いたことはいままでなかった。 一番最初、破瓜の時の痛みを除けば。 血を啜られているわけではない。寧ろ、何かを押し込まれているような重い痛み。 身体を捩り逃れようとするが、押さえつけられた大腿はびくともしなかった。 紅色の布を握り締め、きつく目を閉じる。流れた涙の場所だけ、シーツの色が濃くなってゆく。 痛みに遠のきそうになる意識。それを引き戻すものまた痛みだった。 眦から零れる雫が尽きた頃、慢性的となっていた鈍痛がようやく遠ざかった。 玉の汗が浮かぶ琴音の額に乙夜の手が乗る。 「――いつ、や、く……なに、した、の……?」 薄っすらと瞳を覗かせた琴音の問いに、乙夜は何も答えてはくれなかった。 かわりに与えられたのは、優しいキスと、艶かしい愛撫。 乙夜の指先が琴音の蜜口をやわくほぐす。 酷い痛みに苛まれながらも、琴音の蜜はまだ枯れていなかった。 再びの愛撫に、とくりとあふれ出す。 「……っ」 かっと全身が熱くなる。羞恥と快楽。頬を朱に染めながら、琴音は乙夜を拒む事は出来なかった。 体が溺れているわけではない。心が溺れている。 「あ、あ……んっ」 乙夜の昂ぶりが焦らされることなく、口付けと共に蜜口に入り込んでくる。 優しいキスと、愛撫。初めてのときよりも怖いと思った。 優しくされればされるほど、別れが間近に感じられる。 「いや、乙夜君、や、だ」 身をよじって琴音は乙夜を拒絶する。 「今更? でもやめるつもりはないよ」 かすれた声で囁いく乙夜に、琴音は首を振った。 「ちがう、ちがうの。……これで最後、みたいなこと、しないで。やさしくしないで――やだ、まだ、お別れ、したくない」 常に別れの予感と隣り合わせの関係なのだという事は、おそらく乙夜が思うよりも深く琴音の心に根ざしている。 優しくされればそれが最後になるのかもしれないと琴音は怯えていた。 「最後じゃない――これが最初だよ」 乙夜にかき抱かれる。その腕の中で、頭を横に傾げた琴音は首筋をさらした。 辰巳に少なくはない量の血を啜られていたが、ためらいはない。 辰巳に襲われ、琴音は乙夜が他の同族とは違うのだと初めて悟った。 餌に違いはなくとも、多分大切にされている。 玩具を丁寧に扱う程度の意味しかないのかもしれない。 辰巳が琴音の血を薫り高いと言っていたことを事実とするなら、餌を長く楽しみたいというだけなのかもしれない。 それでも、嬲っているはずの手はいつでも優しかった。泣きたくなるほどに。 首の付け根あたりに乙夜の唇が触れる。けれど小さな痛みはやってこなかった。 かわりに蜜口にあったはずの昂ぶりが、ぐっと奥まで入り込んできた。 二人分の重量と動きにベッドが軋む。 圧迫感。押し付けられた腰。身のうちが乙夜で充たされる。 焦らされる事なく揺すられて、掠れた喘ぎ声が零れる。 全てを暴かれる、全てを見られているような、けれど同時に、ひどく乙夜が遠いような、奇妙な錯覚。 自分の中で胎動する乙夜を感じながら、琴音は両腕を伸ばした。 「乙夜君を抱きしめたい――抱きしめさせて」 切羽詰った声で訊く琴音に、乙夜が動きを止める。 無言のまま琴音の手首をつかんで自分の首に回させた。 どこもかしこもが火照っている。熱くてたまらない。 乙夜の精を薄い膜越しとはいえ身体の奥に受け止めて――そこまでが琴音の限界となった。 |
| (2007.8.2 up) Back ‖ Next |
:: top * novel :: |
Copyright (C) 2007 kuno_san2000 All rights reserved. |