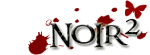 ― ノワール・2 ― 刻印(2) |
「ここが違ってるからだよ」 「――あ、」 広げたノートの上を、乙夜の繊細な指先が容赦なく指し示す。 行きつ戻りつしていた琴音の思考は一点に集中した。 ああ、こんなところを間違えていたのかと下唇を噛む。 「わかった?」 乙夜に問われ、琴音は小さくうなずいた。 「次に間違えたらお仕置きだから、がんばった方がいいよ」 もう一度きゅっと噛もうとした唇の上に、乙夜の親指がゆるりと乗せられた。 輪郭をなぞっていく指先は、悪癖は止めなさいと暗に言っている。 耳を赤くする琴音に、乙夜が謎めいた微笑を浮かべた。 琴音がぱたりと本屋通いを止めてから一週間が過ぎていた。 乙夜は約束どおり家庭教師としての役割を果たしてくれている。 それはとても懐かしく、けれど昔は到底わかりえなかった乙夜の一面を知ることにもなった。 常に本心をみせてくれてはいない、と感じる。 昔はどうだったのだろう、こんな風に微笑む人だったろうか。 昔の乙夜の何をみて何を好きになったのか、深く考えれば考えるほど輪郭は曖昧になるのに、気持ちだけは揺るがない。 「琴音、ちゃんと考えてる?」 「――え?」 はっとして首をめぐらせると、シャーペンが手から滑り落ちた。 乾いた音を立てローテーブルの縁まで転がったそれは、フローリングの床へ向けて瞬く間に落下を開始し、ぶつかる寸前で乙夜の手の中へ受け止められた。 乙夜の溜息。ごめんなさい、ありがとうと立て続けに言って、琴音が慌てて手を伸ばす。 すっと乙夜の手が遠ざかり、バランスを崩した琴音は乙夜の胸に抱きとめられた。 白いブラウスの上から乳房の膨らみをなぞられ、ぶるりと身が震える。 制服のプリーツスカートが押し上げられ、白い腿があらわになった。 「……まだ、後、一問ある、よ」 「余所見をしたからね。ペナルティだよ」 「――昔は……こんなペナルティじゃ、なかった、のに」 「そうだね、あの時は秘密を一つずつ打ち明けてくれたんだよね。――ね、琴音。今の秘密は、何?」 「全部言っちゃったもん……もう、秘密なんてない……よ……、んっ」 薄く開いた唇に乙夜のそれが重なる。 口腔内に入り込んできた柔らかなものに、琴音は自分から舌を絡ませた。 ショーツの上から指先で中心をなぞられ、乙夜の肩に乗せた手に力がこもる。 直接触ってはもらえない。もどかしい刺激。 それでも慣らされた愛撫に、薄い布は湿り気を帯びた。 布越しに蜜口へと入り込んでくる指に押され、ショーツの中が蜜で濡れる。 琴音の頬が上気し、耐え切れないあえぎ声が漏れ始めたところで、唐突に乙夜の愛撫は終わった。 ぺたりと座り込んだ琴音は肩で息をしながら目を潤ませる。 中途半端に煽られた状態は、正直な所かなりつらかった。 「続きをしようか」 「……う、ん……」 のろのろと起き上がり、ローテーブルの前に座る。 乙夜が琴音に与えるペナルティは、間違えれば間違えるだけつらくなる。 かといって、昔と同じバツを与えられたとしても答えられる自信はなかった。 琴音が持っている秘密。 強いて言うなら乙夜とのこの関係。それに琴音自身の気持ち――昔も今も言えなかった乙夜への恋心だ。 前はもっと他愛のない秘密があった気もするが、今の琴音には思いつかない。 シャーペンを持ちノートに向かう。 身体の火照りを意識しないようにして落ち着こうとするが、時折波のように寄せてくる疼きはなかなか静まってくれなかった。 問題を解こうと走らせたシャーペンの先が幾分震え、文字が歪になる。 もう少し落ち着こうと大きく息を吐いて、参考書を片手に取った。 綺麗にカバーの掛かった本。最後に行った日に初めて口をきいた人を思い出す。 ぱらりと表紙をまくり、テーブルの上に置こうした。乙夜の手がそれを押しとどめる。 驚いて乙夜を見ると、すべてを見透かすような双眸にぶつかった。 「何を――誰を考えていたの、琴音」 「え……あの、本屋に新しい店員さんが、いて」 「そう、どんな人」 乙夜の指先が触れている手の甲にちりちりとした熱さを感じる。 針先で軽くつかれているような奇妙な感覚だった。 「人当たりの、よさそうな、人……だと思う」 「――琴音、いまから僕の言うことを良く聞いて」 乙夜が一旦言葉を切る。琴音はわけがわからずただ黙していた。 「その人には近づいちゃいけないよ、わかった?」 どうしての一言を思わず飲み込んだ。静かな圧力に、琴音は頷かざるを得なかった。 「さあ、じゃあ後はここだけ。終わったら食事にしよう」 とん、と問題を差して、乙夜がにこりと笑みをみせる。 食事の意味するところを理解した琴音は、家庭教師と生徒というこのままの時間が終わって欲しくないような、終わって欲しいような不可解な気持ちになりならが、もう一度あいまいに頷いた。 *** 「琴音」 くしゃくしゃに泣き濡れているはずの自分をみられたくはなくて、琴音はふいっと顔をそらした。 両手は一括りにされ縛られ、肌蹴たブラウスから除くブラはホックこそ外されているが、腕から抜くことはできず、頼りなげに琴音の肌を掠める。 「もう自分で入れられるよね?」 向かい合って座る乙夜の囁きは、迷いを蕩けさすように甘い。 それでも琴音は左右に頭を振り、頑なに乙夜の要求を拒絶する。 強引に振り向かされ、口付けられ、再度求められても――琴音は頷けなかった。 「あまり我慢をしていると、後がつらいと思うよ」 「……っ」 とがめるというよりもむしろからかうようにささやかれ、琴音の頬が赤らむ。 乙夜が軽く膝を上げると、跨った琴音の中心が刺激され、甘く疼いた。 「ぅ、ん……」 かみ殺しきれなかった声は色香を含み、艶めいている。 乙夜がいたずらに弄んだ花芯は溢れた蜜で濡れていた。 綻んだ花弁を乙夜の指で開かれる。 何度繰り返されても、秘した場所に触れられる羞恥には慣れることができない。 握り締めた手の甲を口元にあて、耐える。 けれど、既に充血した芽を擦られ、たまらずに悲鳴が漏れた。 「言った筈だよ、我慢するとつらいって」 「ん、やぁ……」 「いや? でも、僕の指をとてもきつく咥え込んでいるね」 嘲るように言われ、琴音の肩がびくっとはねる。 乙夜の指がぐちゅっと音をさせ琴音の中から引き抜かれた。 耳元の声に促されるまま、緩慢に腰を持ち上げる。 蜜口に硬い昂ぶりが触れ、離れた。 「……いつ、や……く」 「駄目。僕からはあげないよ。――ちゃんと自分でいれてごらん」 耳朶を食まれ、耳の中に柔い舌の感触を覚え――琴音は、落ちた。 身を寄せ、哀願するように乙夜の唇に自らのそれを押し付ける。 「琴音」 かすれた低音。もっと聞きたい、と飢えたように思う。 縛られた手で乙夜自身に触れ、蜜口の中に迎え入れようと腰を落とす。 慣れてない行為に何度か失敗して、乙夜が腰を支えてくれてようやく先端をおさめた。 ぐずぐずに蕩けた中に、ゆっくりと根元まで乙夜を沈める。 けれどその先はどうしていいかわからなくて。 それでも乙夜を感じたくて琴音はゆるゆると身体を動かした。 これが自分の望んでいたこと。浅ましくて淫らで。 何よりも乙夜には知られたくない、願望。 もう、無理やりではなく、琴音は乙夜に対して足を開く。 この人が欲しいと――欲しくて欲しくてたまらないと、心が啼く。 手に入れることはできないとわかっているのに。 浅ましい。浅ましくて、浅ましくて。けれど――この人が、好きだ。 「乙夜、くん」 乙夜に抱きとめられた琴音は、小さく儚く呟いた。 皮膚に冷たい牙が触れ、つぷりとわずかな音をたてると鉄の匂いが鼻をつく。 琴音の目尻から透明な涙が一滴、こぼれた。 *** 薄い紅に染まる街は、雑多な気配と生活の匂いを染み込ませて宵の口に入ろうとしている。 煉瓦敷きの歩道を人ごみをすり抜けるようにして進む琴音の足取りはとても軽い。 今日渡されたばかりの順位表が、肩からかけたトートバッグの中にある。 驚いたことに、下がってしまった分を取り返しただけではなく、乙夜との今の関係が始まる以前よりも成績はあがっていた。 乙夜の教え方がうまいことはもちろんだが、琴音にとって家庭教師と生徒という懐かしい関係が与えてくれた影響も大きかったらしい。 我ながらなんて単純なんだろうと自分に呆れ、それでもうれしい気持ちに違いはなく、これでまた乙夜の元へ通えるのだと思うと心が浮き立った。 乙夜に早く伝えたかった。けれど今日は何も言われていない。 行ってもきっといないだろう、それに、迷惑かもしれないと考えてしまえば、通いなれた道に向うことは出来なかった。 次回会う時まで大切にしまっておこうと自分を納得させて、帰路を辿っている。 大通りから角を曲がり、馴染んだ路地になる。 クリーニング店と花屋のならびに、馴染んだ書店の看板が見えてきた。 琴音の歩調がゆるりとしたものになる。どうしよう、と迷いながら書店を見上げた。 緑色の地色にオオヌキ書店と白抜きされた簡素な店舗看板。 乙夜に寄り道をしないよう言われてから、一度も来ていない。 入用な本は学校近くの大手小売店ですませるようにしていたが、落ち着いた佇まいと月日を重ねた店内の匂いが不意に恋しくなった。 ――どうしよう。あのひと、いるのかな。 なぜかはわからないが、近づくなと乙夜は言った。 自分の言い方になにかまずいところでもあったのだろうかとも考えたが、人当たりのよさそうな人としか言っていない。 いくら考えても理由が思いあたらかなった。 ガラス張りになっている店舗の入り口近辺からレジのある場所をそっと覗き込む。 対応をしているのは見知った店主だ。 書棚の並んだフロアにも例の人と思しき姿は見当たらない。 ほっとして息をついて、琴音は寄っていこうと決めた。 「こんにちは」 「……え?」 耳に心地よい低めな声にぱっと振り返ると、白を基調とした細いストライプ柄に目を奪われた。 かっちりと着こなされたシャツ。細身のジーンズは藍で染められ、持ち主の立ち姿をすっきりと見せている。 立ち尽くしたまま愕然としている琴音に、男はもう一度、こんにちは、と問いかけるように言った。 「こん、にちは」 ぎこちなく返した琴音を気にする風もなく、辰巳はにこりと笑った。 「近頃いらっしゃらないからどうしたのかなと思ってたんですよ。テストはどうでした?」 「あ、はい。……予想以上に、よかった、です」 そうですかそれは良かった、と嬉しそうに言い、寄っていかれるんですよね、と店の入り口を指差した。 しっかりとそちらを向いていた琴音は、違いますとも言えずうろたえていた。 けれど、自動ではないドアを辰巳により開かれ、あまつさえ入ることを促すように脇に退かれては、入るよりなかった。 店内には二、三人の客しかいない。 伝票を手にした店主が琴音に気付き、いらっしゃいませと、馴染み少し嗄れた声で言った。 辰巳はごゆっくりと琴音に言い置き、店の置くにある事務所を兼ねているらしい倉庫へ消えていった。 紙とインクの匂い、特に目当てを決めているわけではなく、軽い読み物の入った書棚の間をゆるゆると回る。 気になったものを抜き出してさっと目を通す。 まだ読んだことのなかった古典ミステリを一冊選び出す頃には、陽は落ち、宵闇が満ちていた。 レジには辰巳がいる。 いささか緊張しつつ本を差し出すと、手際よく会計が済まされた。 「もう外が暗いですね。大丈夫ですか? この先、街燈があまりないでしょう」 「あ、はい。いえ、家がもうすぐですから。お気遣いありがとうございます」 「そうですか、お気をつけて」 ペーパーカバーのかけられた品物を受け取り、会釈してレジを離れる。 ほっとため息を洩らし、疑問が湧く。乙夜が気にするようなことは何もないように思えた。 「また来てくださいね、琴音さん」 財布を鞄に収めようとしていた琴音は目を見張り、足を止めて辰巳を振り向いた。 辰巳は既に、レジに寄ってきた男性の接客をはじめている。不審なところなどどこにもない。 ――私、あの人に名前……言った? 聞き、間違い……? 予約注文を受けたらしい辰巳は、あわただしく動いている。 釈然としなかったがそれ以上は話しかけることもできず、琴音は今度こそ帰路に着いた。 |
| (2007.7.31 up) Back ‖ Next |
:: top * novel :: |
Copyright (C) 2007 kuno_san2000 All rights reserved. |