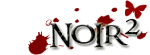 ― ノワール・2 ― 刻印(1) |
「こんにちは」 耳に心地よい低めな声は、小さく流れる有線放送の中に交わることなく、はっきりと耳に届いた。 それが自分に向けられたものだと気付き、琴音はシンプルな二つ折りの革財布から札を取り出そうとしていた手を止めた。 驚きながら顔を上げ、戸惑いに僅かな間があく。琴音は、小さく会釈しながらこんにちはと挨拶を返した。 レジカウンターの向こうで、オオヌキ書店と白抜きされた緑色のエプロンをつけている背の高い細身の男性店員は、にこりと穏やかに笑っている。 人当たりが良く手際も良い二十代後半と思われるその店員を、琴音は良く通っているこの書店でここ数日の間に見かけるようになっていた。 左の胸元止められた白い小さなネームプレートには『辰巳』と丁寧な筆文字で書かれていて、会計時の手持ち無沙汰に何気なく見ていた琴音は名前まで覚えていた。 けれど、声をかけられるとは思っていなかった。 すっかり顔馴染みになった四十がらみの店主と話すことはあったが、今レジにいる男性とは、義務的なやり取り以外の会話を交わしたことはない。 「昨日もいらっしゃいましたよね、お近くにお住みなんですか?」 「あ、はい……ここの前が帰り道で」 支払いをしながら応じる琴音の前で、手早くペーパーカバーを掛けられた参考書がカウンターに置かれ、清算が行われる。 会話の最中も、手がとまることはない。 「ああ、そうなんですか。不躾な事をお聞きしてすみません。昨日だけでなくここ数日毎日いらしていたでしょう?」 すっかり顔を覚えられていたのかと、なんだかばつが悪くなり、琴音の頬はほんのりと赤らんだ。 テスト週間が近づいていることもあり、必要な参考書を求めて随分足しげくの書店へ来ている。 琴音が店員の顔を覚えたように、当然、相手にも覚えられていて不思議はない。 「そろそろテストが近くて」 「なるほど。この参考書、よく売れてますよ。勉強頑張って下さい」 「ありがとうございます」 人好きのする店員に微笑みながら、けれど琴音の心中は少し複雑だった。 今回は絶対に頑張らなければいけない、と考える一方で、本当に大丈夫なのかと不安が募っていく。 どれだけ知識を詰め込んでもそれは拭えない。 目を伏せた琴音の前に、つい、と浅黒い手が出された。 白いレシートと銀と茶の硬貨。琴音があわてて受取ろうとすると、その手は軽く閉じられた。 驚いて見上げた先には、やや首を傾げて変わらずに笑みを絶やさない店員がいる。 「宜しかったら、明日もぜひお越し下さい。売り上げに貢献していただけるのは大歓迎です。――残念ながら僕の時給はかわらないんですけどね」 最後を茶目っ気たっぷりに言われ、琴音は思わず声を立てて笑ってしまった。慌てて口元を押さえる。 小さな街角の書店だが、品揃えの内容が硬いためか客層の年齢は高い。音楽すら邪魔にならない程度の音量でしかない店内は常に静かだ。 「はい、おつりになります」 にっこりと笑顔で渡された小銭を受取る。 ありがとうございました、の声に琴音は軽く会釈で返した。 カバーの掛かった参考書を鞄にしまい、店を出る。 幾つかのビルが並ぶ間から、沈みかけた夕日が覗いていた。 雑多な街中、赤く染まる空の下を歩き出す。 琴音の向う先は自宅ではない。 まっすぐに目指すのは、乙夜の家だった。 *** 「また寄り道してきたね?」 「……あ、ん……んんっ」 「ここにくるのはそんなに嫌?」 「あ、違……っ、ん、乙夜く……違、う」 ぎっとベッドが鳴る。 中を抉るように後ろから突かれて、琴音は喘ぎながら喉を逸らした。 ひじを突いた姿勢で腰を高く持ち上げられ、乙夜を受け入れている。 後ろからまわされた長い指が悪戯に琴音の花芯を弄ぶ。 零れ出た蜜が琴音の内腿を伝っていく様は、薄暗い室内でひどくなまめかしい。 乙夜が動くたび、淫靡な水音が耳に届く。苦痛と感じるほどの甘い疼きに琴音の背がびくりとしなった。 「ふ、あ……、ん、や……っ」 何度目かの絶頂を向かえ、生理的な涙が流れ落ちた。 ヒクリと痙攣する身体をそれでも乙夜は離してくれず、ぎりぎりまで琴音の理性を奪う。 「……や、もう……ゆるし」 「嘘は駄目だよ、琴音。ほら、また僕を締め付けてる」 嘲笑うかのように乙夜が激しく突いてくる。 琴音の喉から悲鳴が漏れた。与えられるのは、痛み。それ以上の、快楽。 猥らな狂態だったと、ベッドから降りればいつも後悔する。 けれど乙夜に抱かれている最中は、どうしても自分を止められない。 知っているのは乙夜の愛撫だけ。凶暴で優しくて気まぐれで。 けれど、翻弄される自分を琴音は戸惑いながらも受け入れている。 目の前が、白くなった。シーツをきつく握り締めた琴音の両拳も白くなる。 肩口にちくりとした痛み。波が引くように力の抜けていく琴音を、まだ繋がったままの乙夜が背後から抱きとめる。 見えてはいない。 けれど乙夜の喉がこくりと嚥下したその瞬間が、琴音にはわかった。 *** すっかり情事の跡を消した乙夜が、なぜか再びベッドの傍に戻ってくる。 素肌にタオルケットを巻いてうつぶせていた琴音は、半ば以上まどろみの中に浸りながら、珍しい、と思った。 一度ベッドを降りた乙夜が、意識のある琴音を気にかけてくれるのはとても稀な事だ。 まだ起き上がる気には到底なれなれず、乙夜の動きを目だけで追う。 それでも乙夜が傍に来る、それだけでたまらなく嬉しいと感じてしまう。 息を深く吐いて、眠気を追い払おうとする。けれど、琴音の努力はまったく無用だった。 ベッドの端に腰掛けた乙夜に突然耳朶を食まれた驚きで、一気に眠気は吹き飛んだ。 「ねえ、琴音」 「な、な、に……?」 慌てて上半身を起こして、食まれた右耳を両手で押さえる。 きつく咬まれたわけではもちろんなく甘咬みされたのだが、逆にその方が行為としてはなまめかしい。 肌をちろりと舐めていった舌の感触は、琴音の動揺を誘うに充分過ぎた。 抱かれている時には甘さを覚えるそれも、嵐のような熱が過ぎ去った今されるのは、なんとも気恥ずかしい。 「どこに寄り道してきたの?」 赤くなる琴音を気にする風もなく、乙夜が上体を寄せてくる。 「……あの、本屋、へ。でも違うの、来る時間を遅らせたいわけじゃなくて……その、成績が……下がって……参考書、を」 まるで研磨した艶やかな宝石のような二つの目に間近で見つめられ、琴音はいたたまれずに俯いた。 乙夜には黙っていたが、前回の定期試験で琴音は順位を落とした。 今までも優秀というわけではなかったが、そこそこだった成績は乙夜と関係を持った時期を境にゆるゆると下降した。 せっかく乙夜に家庭教師をしてもらって入った高校だというのに自分が情けなくて仕方がない。 それだけに事実を告げるのは少なからず勇気のいることで、けれど、誤解されたままいたくなかった。 それに琴音の母と乙夜は、今も道で会えば立ち話をしているという。母から告げられるよりは自分で話したほうがよほど良い。 「ああ……勉強している間はなかったよね」 納得したようにくすりと笑われ、琴音の頬が赤くなる。 この頃は乞われるまま頻繁に乙夜の元へ通っていた。 一度に求められる血の量は僅かなので貧血になるようなことはないし、嫌なわけではないのだが、如何せん時間は有限だ。 それに、部活で帰りが遅くなっていることになっているが、このまま成績が思わしくないようであれば、両親からやめるように言われるのも時間の問題だった。 乙夜に会えなくなるかもしれないと思うと、胸が痛い。 手繰り寄せたシーツをきつく握り締め身を縮め、琴音はきゅっと下唇をかみ締めた。 ふいに頤を乙夜につかまれ、上向かされる。 「その結果が、目の下の隈?」 親指が琴音の下瞼をそっと撫でた。 喉をくすぐられた猫のように陶然と身を任せてしまいそうになる。 いけないことだと、琴音は自分を戒めた。 乙夜にとって自分は餌にしか過ぎないのだから、重荷になってはいけないのだ、と。 「まったく馬鹿だね、琴音は。素直にねだれば、昔のように僕が教えてあげるよ?」 「――え?」 迷惑をかけたくない、自分の立場を忘れてはいけないと思ったばかりのところに思いもかけないことを言われ、琴音は目に見えてうろたえた。 本心を見せない、それでいてあきれたような笑みを刻んだ乙夜は、じっと琴音を見つめている。 「……いいの?」 こくりと喉を鳴らしおずおずと承諾を求めた琴音に、ちゃんと素直にねだってくれればね、と乙夜は啄ばむように口付けた。 琴音の頬に掛かっていた髪を一房持ち上げ、さらさらと手のひらからこぼしながら乙夜が笑む。 「だから寄り道はしないで、急いで僕の元へおいで」 「――うん」 まるで昔の乙夜に戻ったかのようで。 そっと触れた乙夜の手に頬を預けると、琴音は小さくうなずいた。 |
| (2007.07.30 up) Back ‖ Next |
:: top * novel :: |
Copyright (C) 2007 kuno_san2000 All rights reserved. |